はじめに
中小企業のM&Aを検討する際、多くの買い手が見過ごしがちな盲点があります。それが「関連当事者取引」です。特にオーナー企業では、社長個人と会社との間の取引が頻繁に行われる傾向にあり、その中には企業価値を大きく歪めるリスクが潜んでいるケースが少なくありません。不透明な資金の移動や、実態と乖離した取引は、M&A後に深刻な問題を引き起こす可能性があります。
買収してから「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、デューデリジェンス(DD)の段階でこれらの取引を正確に把握し、潜在的なリスクを評価することが重要です。
本記事では、中小企業M&Aに潜む関連当事者取引のリスクに焦点を当て、財務DDにおける具体的な調査ポイントや、発見されたリスクへの対処法を解説します。安全なM&Aを実現するための参考材料としてご活用ください。
関連当事者取引とは?
まず、「関連当事者取引」の基本的な定義と、なぜそれが中小企業のM&Aにおいて重要な論点となるのか、その背景と構造について解説します。
関連当事者取引の定義
「関連当事者取引」とは、会社とその経営陣や親族といった特別な関係にある人々や企業(=関連当事者)との間で行われる取引のことです。ここでいう「関連当事者」には、具体的に以下のような個人や企業が含まれます。
- 会社の役員とその近親者
- 社長が実質的に支配している関連会社・子会社
- 会社の意思決定に重要な影響を与える主要株主
そして、これらの関連当事者との間で行われる、商品・サービスの売買、不動産の賃貸借、金銭の貸し借り、役務提供といった取引全般が「関連当事者取引」に該当します。
これらの取引は、その特殊な関係性から、第三者間取引では通常用いられない条件で設定されている可能性があります。したがって、DDを実施する際は、企業の正常な収益力や財政状態を正確に評価するため、これらの取引に対して特に慎重な検証が必要となります。
中小企業で関連当事者取引が起こりやすい理由とそのリスク
中小企業、特にオーナー企業において、関連当事者取引は決して珍しいものではありません。その背景には、経営者個人の資産と会社の資産の境界が曖昧になっていたり、社内のチェック体制(ガバナンス)が十分に機能していない実態などがあります。また、オーナー一族の税負担を軽減したり、個人的な便宜を図ったりする目的で、意図的に関連当事者取引が活用されるケースも少なくありません。
これらの取引はM&Aの局面で下記のようなリスクにつながる可能性があります。
- 企業の真の実力が見えなくなる
関連当事者との取引を通じて利益が不当に操作されている場合、損益計算書に表れている業績と、会社が本来持つ正常な収益力とがかけ離れてしまいます。これに気付かず企業価値を評価すると、高値掴みをしてしまう恐れがあります。
- M&A後に業績が急変する
相場より有利な条件で続いていた取引が、M&Aを機に解消または適正化された結果、これまで通りの収益を確保できなくなり、業績が悪化するケースです。買収後に事業計画が根底から覆されることにもなりかねず、極端な場合には、関連当事者取引が無くなった結果、対象会社のビジネス自体が立ち行かなくなることもあります。
- 簿外債務や税務リスクの温床になる
不適切な取引が税務調査で否認された場合、過去に遡って追徴課税や延滞税といったコストが発生することがあります。これは、財務諸表には表れない「隠れた債務」として、買収後に買い手の予期せぬ負担となる場合があります。
このように、関連当事者取引はM&Aの現場において「見えにくい落とし穴」となることがあります。買い手側としては、どれほど小さな取引であっても油断せず、慎重に内容を確認する姿勢が求められます。
財務DDで注意すべき関連当事者取引のパターン
財務DDで特に注意して調査すべき、問題を含んだ関連当事者取引の具体的なパターンを紹介します。
不透明な資金移動
- 社長・役員への貸付金・仮払金
回収の目処が立たない貸付金や、使途が不明瞭なまま放置されている仮払金は、実質的に役員への資金流出(賞与など)と見なされる可能性があります。これにより、本来であれば会社に残るべき資金が失われているおそれがあります。 - 社長・役員からの借入金
相場から大きく外れた利率が設定されている(極端に高い、あるいは無利息など)ケースがあります。また、契約書のない口約束での借入は、M&A後に突如返済を求められ、資金繰りに深刻な影響を与えるおそれもあります。
不自然な価格での不動産・資産取引
- 社長所有不動産の賃借
会社が社長所有の不動産を事務所として借りている場合、賃料が相場に比べて不自然に高額、または低額に設定されているケースです。こうした取引は企業の正常な収益力評価を阻害する要因となります。 - 会社資産の無償・低廉な提供
社長や親族が、会社の車両や不動産などを無償または相場より安く私的に利用しているケースです。これは本来会社が得るべき収益機会の損失であり、役員への経済的利益の供与として税務上のリスクも伴う行為と考えられます。
営業取引を通じた利益操作
- 関連会社との取引
社長が経営する別の会社との間で、意図的に利益を移転させるための価格設定(高値での仕入れ、安値での販売)が行われるケースです。その他にも、実態のないコンサルティング料や業務委託費の支払いなどの行為も営業取引を通じた利益操作の典型的な手口です。
経費の公私混同
- 社長やその親族のプライベートな支出(車の購入費や維持費、個人的な飲食費、旅行の費用など)を、会社の経費として処理しているケースです。会社の経費が実態以上に膨らみ、収益力を過小に見せる原因となります。
不適切な役員報酬・給与
- ゴースト社員への給与支払い
勤務実態のない、あるいはごく限定的な親族を従業員として登録し、給与を支払うケースです。不正な人件費計上を通じて、会社資金を親族に流す手段として使われることがあります。 - 過大な役員報酬・退職金
業績や同業他社と比べて明らかに過大な役員報酬や退職金が設定されているケースです。M&A直前に退職金規定を変更し、創業者利益の確保を図る例もあり注意が必要です。
財務DDにおける関連当事者取引の調査手法
これらの疑わしい取引に対して、財務DDではさまざまな手法を通じてその内容を確認します。具体的な調査手法について、以下の表にまとめました。
| 調査手法 | 主な調査対象 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 勘定科目・総勘定元帳の調査 | 役員貸付金、仮払金、支払手数料、福利厚生費など | 取引の相手先、金額、頻度、不自然な点がないかを確認します。 |
| 契約書など原始記録との突合 | 取締役会議事録、稟議書、契約書、請求書など | 書類と会計帳簿を照合し、取引の意思決定プロセスや取引の実態が伴っているかを検証します。 |
| 関係者へのヒアリング | 経営者、経理担当者、場合によっては取引の相手先 | 帳簿だけでは不明な取引の背景、目的、意思決定の経緯などを直接確認します。 |
| 取引条件の妥当性評価 | 関連当事者との個別の取引条件(賃料、利率、価格など) | 第三者間取引や市場価格(相場)と比較して、取引に経済合理性があるかを客観的に評価します。 |
こうした調査を通じて、帳簿上には表れにくい関連当事者取引のリスクを可視化し、企業の実態を正確に把握することが財務DDの重要な役割です。
買収後のトラブルを未然に防ぎ、公正な企業価値評価を行うためにも、丁寧な調査が欠かせません。
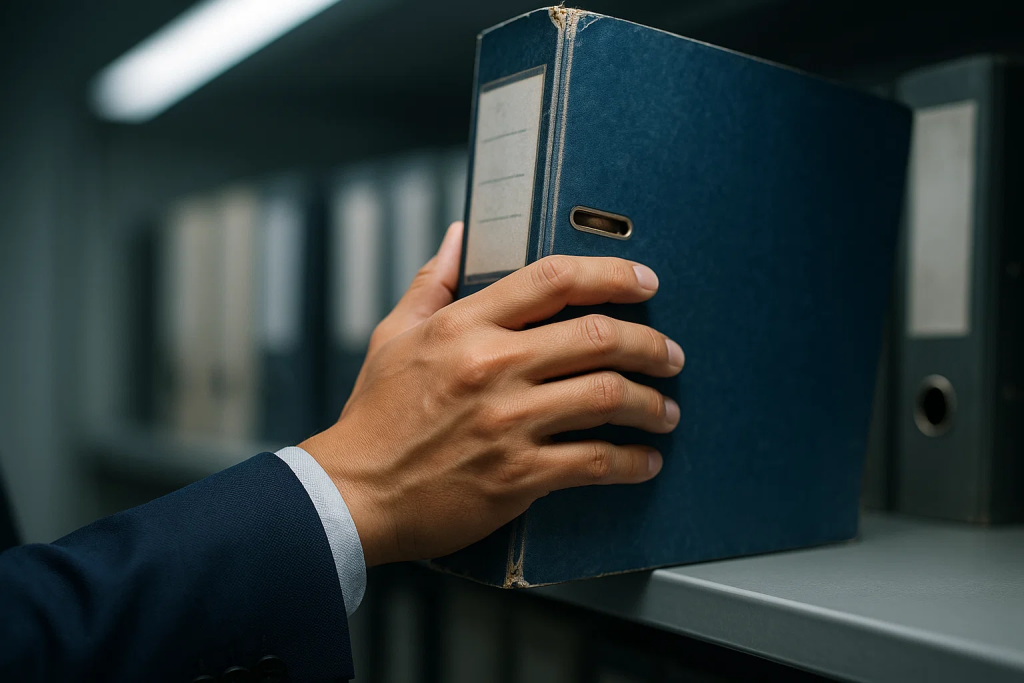
DDで明らかになったリスクへの対処
財務DDで関連当事者取引に関する潜在的なリスクが明らかになった場合、買い手はどのように対応すべきなのでしょうか。ここでは、そのリスクへの対処法について解説します。
1.取引の解消・取引内容の見直し
問題のある取引を解消したり、条件を適正な水準に見直すよう売り手に求める対応です。
たとえば、経営者や親族への不明確な貸付金がある場合は、M&Aの最終合意(クロージング)の条件として全額返済を求め、リスクを解消した上で最終合意に進むのが一般的です。
2.企業価値評価(バリュエーション)への反映
正常収益力をもとに企業価値を再評価し、買収価格に反映させるという方法です。
関連当事者取引でかさ上げされた利益は除外し、実態に即した価値を算出します。回収不能な貸付金などは、純資産から控除する価格調整も一般的です。
3.契約時の条項によるリスクマネジメント
M&A契約に特定の条項を設け、将来のリスクに備える方法です。特に関連当事者取引は無償で行われるケースも多く、表明保証によるカバーが重要になります。
- 表明保証(Representations and Warranties)
売り手に対し、開示された関連当事者取引がすべてであり、適法かつ適切に行われたことを表明・保証させる条項です。万一、内容に誤りがあれば、契約違反として責任を問うことができます。 - 補償(Indemnification)
表明保証違反により買い手に追徴課税などの損害が発生した場合に、その損害を売り手が補償することを定める条項です。
(関連記事:「M&A契約における「表明保証」とは?財務・税務DDの結果をどう活かすか解説」)
4.買収後のPMI(経営統合)計画への織り込み
買収後の経営統合(PMI)プロセスにおいて、あらかじめ新たな取引ルールや承認フローを整備し、ガバナンス体制を強化しておくという対処法です。これにより、同様の問題の再発を防ぎ、健全な経営基盤の構築につなげることができます。
こうした対処を適切に講じることで、買収後に予期せぬトラブルが発生するリスクを抑え、M&Aの安定的な着地につなげることが可能になります。関連当事者取引は軽視できない論点であり、DDの段階で丁寧に向き合うことが重要です。
まとめ
本記事では、中小企業M&Aにおいて見落とされがちな「関連当事者取引」について、そのリスクから具体的な調査手法、対処法までを解説しました。
関連当事者取引は、企業価値の正確な把握に欠かせない重要な論点です。帳簿の数字だけで判断せず、取引の実態や経済的な妥当性まで丁寧に確認することが、M&Aを成功に導く鍵となります。
財務DDの段階でリスクを適切に把握し、必要な対処を講じることで、買い手・売り手の双方が納得できる公正な条件での合意が可能になります。
筆者の経験上、中小企業の売り手は、関連当事者取引の自覚がないまま行っていることが少なくありません。ヒアリングで「関連当事者取引はありますか?」と尋ね「ありません」と回答を受けたのにも関わらず、実際に総勘定元帳などを確認すると、親族との取引が数多く見つかることがあります。
中小企業にとって関連当事者取引とはごく普通のことであり、「問題となる取引である」という認識が乏しいことが多いです。
また、ヒアリングの際に不自然な取引に関連する話題になると、急にトーンが下がるなどの反応があり、そうした態度を元に関連当事者取引に絡んだ疑わしい取引を発見する場合も多くあります。そのため、少しでも不自然な取引や違和感のある反応が見られた場合には、その背景や経緯について丁寧に確認を進めていくことが重要です。
関連当事者取引の調査には、会計・税務・法務にまたがる専門的な知見もさることながら、実務経験や疑わしい取引やリスクを発見する能力も求められます。公認会計士や税理士といった専門家のサポートを受けながら、慎重に手続きを進め、後悔のないM&Aを実現しましょう。

